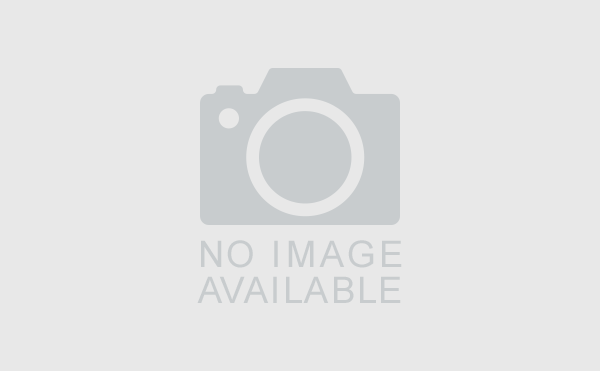蕎麦美学のコンサルタント・(ご飯炊き)【その1-7】料理人への道
料理人への道、そして蕎麦打ち伝道師へ
(ご飯炊き)【その1-7】

(ご飯炊き)この経験と記憶が、
料理人への第一歩目のような気がします。
子供の頃、公園や神社に おじさんがやって
来ました。
「リヤカー」と呼んでいたと思いますが、
その荷台には・大きな筒状の網と本体には、
高圧をかけ・加熱して一気に解き放つと、
耳を(つんざく)様な巨大な音を立てました、
その頃は「トッカン」とよんでいました。
子供相手に笛を鳴らしながら来ていたようです。
母に小遣い銭をもらい、米を持っておじさんへ
今で云う、米ハゼを作ってもらい食べたものです。
お米もこの様な食べ方も昔からありました。
≪前回の続き≫
幼い記憶の中に、五右衛門風呂がありました。
丸い大きな鉄釜、大人一人がやっと入れる
大きさで直火炊きの風呂釜です。
湯船の上には、木の丸いスノコが浮かんで
いました、最初はなんでこんなものが入って
いるの?と萎靡かしげに思い見ていると、
これは足で沈めながら入るのだと言われました。
現在のように対流式であれば底は熱くは無い
が直火炊きなので、素足で入ろうものなら
足の裏が熱くて入れた代物ではないでしょう。
昔の人の知恵であろうと後になり、思い還し
ました。
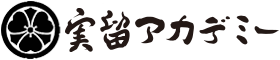
https://www.jittome-academy.jp/
https://www.maruyama-jittome.com/
信州そば手打専科・実留アカデミー
そば打ちと日本料理の職人養成所
専任講師・丸山実留